「協働」について
(1)協働の定義
協働という言葉には同じ音で 「共同」 「協同」 「協働」 があります。しかし、これらは意味が全く違うため、それぞれをしっかり理解することが必要です。
- 協働 … 立場も活動も違うが「課題・目的」が同じ
- 協同 … 立場が異なるメンバーが同じ活動をする
- 共同 … 立場も活動も同じ人が関わる
須恵町が目指すものは皆さんとともに住みよいまちづくりを目指すことであることから 「協働」 を使うこととしています。
(2)「協働」の整理
協働とは、主体者同士が共に悩み、知恵を出し合い、解決することを意味しています。
「協働するということ」には、多くの「段階」が存在すると言われています。あるアメリカの社会学者はその定義を「参加の梯子」という表現で説明しています。
主体者同士がお互いの立場や活動内容を十分理解するために協議を重ね、その理解の上に新しい仕組みや活動を考え、参画する対象者に理解をいただくための説明を行い、はじめて活動が成立するとあります。
協働にいきつくためには、「意見を受け止める・共有されている」というレベルまでいかないと達成できず、この段階を踏まないと主体者間にギャップが生じて、成果の上がる取組みがとれないことが多いとされています。
よって、協働を行うためには相互理解がとても大切であり、そこにしっかり時間を掛けていくことがとても重要であると考えられています。
(3)協働の進め方
では、実際に須恵町では「協働」は行われていないのでしょうか?実は「協働」はすでに行われています。
例えば、「青少年健全育成」という大きな目標を例とします。この大きな目的のために地域では様々な方々が活動をされています。
- 各地域の育成会
「見守り活動」 「子ども会事業」 - 青少年指導員会・糟屋署補導員
「夜間パトロール」 「環境浄化作業」 - スポーツ団体や文化団体
「スポーツ競技指導」 「文化の継承」 - 校区コミュニティ
「防犯パトロール」「危険箇所確認」「こども料理教室」「ガールズフェスタ」
その他の団体でも子ども達への様々な事業を展開しています。どれも「安心安全環境づくり」や「子ども達の健全な心身の発達」「様々なことに触れ合う機会づくり」などが主な目的であり、すべて「青少年健全育成」のためのものであることはいうまでもありません。
「目的」や「目標」が同じで、活動の表現も同じもの、また違うものが存在するが、それらが協力してそれぞれの分野を担当したり、一緒に行動したりしながら相互理解をより深めることで、大きな事業効果を生み出していくこと、これが「協働」です。
「校区コミュニティ」では、各種団体が協議を重ね、「見守り活動」など校区単位での活動が適していると判断された事業についてはすでに「協働事業」としてスタートしていますし、表現が違う事業については各団体でそのまま活動し、その活動報告を一同に会して行う「部会会議」を開催するなど「協働」を着実に行っていただいています。
このように「協働」は皆さんの周りでも実際行われているものであり、これから協働できる事業も多く存在します。
地域や団体、行政、企業等で現在行われている活動において、「協働している事業」「これから協働できる事業」を再度検証し、目的が同じ団体を見つけて協議していくことがとても大切であると考えます。
(4)協働の手法とその内容整理
「協働」を進める上で、最も重要なことは協働の手法を理解することにあります。
それでは実際に「協働」を表現するためにはどのような手法(方法)があるのでしょうか。簡単に整理を行います。
「協働」の手法
(1)協力
「協力」は、主催者の自主性を尊重しつつ、人的または物的支援を行う方法です。
いずれも、お互いの役割分担・責任分担・成果の帰属等を明確にして納得しておくことが必要です。
(2)アダプトシステム
行政等が、特定の財産(道路、公園、河川など)について、地域や民間業者と契約を結び、美化作業や利活用をおこなっていく制度です。
別名「里親制度」とも表現したりします。
(3)共催
「共催」は同じ考え方を持つ主体者同士が「主催者」として協働で事業を行うもので、「共同運営」と言い換えることもできます。
それぞれの主体者が対等な立場で事業を実施することが必要であり。お互いの役割分担・責任分担・成果の帰属等を合意しておくことが必要です。
(4)補助・助成
「補助・助成」は様々な活動団体が行う活動に対し、その意義や目的を理解した団体が、予算的支援等を行う制度です。
(5)後援
「後援」は主催者が行う活動等を理解した団体等が支援を行うことで、「理解を示した」ことを表現する「名義」の表記や、広報活動などの協力を行うなどを通じて、主体者を支援していく方法です。
(6)委託
「委託」は本来主体者が行うべき事業を他の団体等に依頼するものです。
これは依頼される団体が高い専門性や知識、ノウハウを有していることが前提であり、主体者が行うよりもより効果的な成果が得られる場合に行われます。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり課 コミュニティ係
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線342)
ファックス番号:092-933-6579






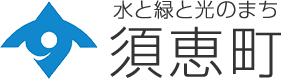



更新日:2024年08月19日