上須恵眼療医 田原養全宅跡
日本四大眼科の一つ、田原眼科の屋敷跡
眼科の祖、高場順世
江戸時代から現在に至るまで、須恵には岡(高場)眼科(須恵区)と田原眼科(上須恵区)という2つの眼科の家系があります。江戸時代には、ともに福岡藩の御典医となり、名声を得ました。田原眼科は江戸時代には日本四大眼科の一つに数えられ、全国に名をとどろかせました。岡家と田原家は、天草出身の高場順世(たかば じゅんせい)から医術を学びました。
江戸時代の治療記録『眼目療治帳』
江戸時代の田原眼科の治療記録『眼目療治帳』が現存します。この資料によると、患者の出身地は、北は北海道から南は鹿児島まで、年間1,000人以上もの患者がこの地に治療(目養生)に訪れたことが記されています。
治療のための宿、「眼病人宿」
「眼病人宿」は、眼病の治療のために岡眼科や田原眼科を訪れた患者が宿泊した宿です。上須恵村や須恵村は、もともとは農村でしたが、全国各地から訪れる患者のために宿屋を営み、後に職業化して屋号を持つようになりました。上須恵では、「肥後屋」「唐津屋」「日田屋」など地名にちなむ屋号、「桝屋」「焼酎屋」など生業に関する屋号が今も残っています。後に、製薬・売薬業を営む家も生まれました。しかし、明治末に田原眼科が移転すると、眼病人宿も衰退し、現在では当時の面影を残すものはごくわずかとなっています。
須恵の目薬「正明膏」
高場順世が考案したとされる目薬「正明膏(しょうめいこう)」は、須恵の目薬として昭和20年代まで盛んに作られました。紅絹に包まれ、蛤に包まれた目薬は、須恵町以外でも広く使われました。大正時代の正明膏の調合を基に復元した近年の研究成果によると、正明膏が抗菌作用、ドライアイに効果があることが明らかになっており、その効能が実証されました。


| 名称 | 史跡 上須恵眼療医 田原養全宅跡 (かみすえがんりょうい たはらようぜんたくあと) |
|---|---|
| 指定年月日 | 平成4年5月1日 |
| 所在場所 | 須恵町大字上須恵637-4 |
| 指定の理由 | 江戸時代の須恵町を語るうえで欠かせない黒田藩医(眼療医)で、地元の人々からも親しまれていた田原家(診療所)宅跡 |
| 現状 | 有形文化財 |
| 伝来その他参考となるべき事項 | 石垣と古井戸を残す以外は更地となっている。前面に薬師堂が残る。 |
この記事に関するお問い合わせ先
社会教育課
〒811-2114
福岡県糟屋郡須恵町上須恵1180-1
電話:092-934-0030
ファックス:092-934-0035
メールでのお問い合わせはこちら






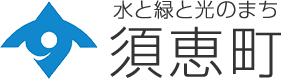



更新日:2024年10月30日