地域の伝統文化を映像で紹介します(須恵町の民俗文化アーカイブス)
「須恵町の民俗文化」シリーズとは
須恵町文化遺産活用実行委員会は、平成24年度より、町内それぞれの地域が大切に守ってきた歴史や文化を映像作品にまとめてきました。これらを「須恵町の民俗文化シリーズ」として公開します。
町教育委員会で撮影、編集したものを含め、須恵町の民俗文化に是非触れていただきたいと思います。
| 民俗文化財の名前 | 画像 | 概要 |
|---|---|---|
| 旅石八幡宮 奉納祇園相撲〈外部リンク〉(大字旅石 旅石八幡宮) |  |
八幡宮の夏の行事です。子どもたちが無病息災を祈願し、境内の土俵で相撲を取ります。消防団員による赤ちゃんの土俵入りも行われ、地域へのお披露目が行われます。 【平成24年7月製作 15分38秒】 平成24年度文化芸術振興費補助金(文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業) |
|
(大字新原 新原地蔵堂) |
 |
新原地蔵堂の地蔵盆です。地蔵堂の仏像は、明治初期の廃仏毀釈の際、宇美八幡宮から難を逃れてやってきました。 【平成24年7月製作 12分46秒】 平成24年度文化芸術振興費補助金(文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業) |
|
(大字新原) |
 |
新原区青年部を中心に早朝から新原地蔵堂の拝殿で綱を作ります。夕方に綱を引き、切れ目からご先祖の霊が西方浄土に帰っていくと伝えられています。 【平成24年8月製作 13分20秒】 平成24年度文化芸術振興費補助金(文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業) |
|
(大字植木 守母神社) |
 |
毎年4月23日、24日の両日、地元の甲植木区の女性たちによる接待などが行われ、訪れた人たちは、子どもたちの健やかな成長を祈願しています。 「守母神社の伝説」は、町の無形民俗文化財に指定されている悲話です。 【平成25年4月製作 12分16秒】 |
|
(大字須恵 須恵宝満宮) |
 |
須恵宝満宮は、応徳2(1085)年に太宰府の竈門神社の神領の北境に勧請されたといわれています。戦国時代に一度荒廃しましたが、小早川隆景が社殿を造営、黒田忠之が若杉山の一部を寄付し、記念に一本の槇の木を植樹したとされます。現在、境内に「殿様槇」として残っています。 奉納相撲は、毎年5月5日に宝満宮境内で行われます。宝満宮の春の大祭の後、地元須恵区子ども会育成会が実施し、個人戦・団体戦が行われます。 【平成25年5月製作 12分51秒】 |
|
(大字上須恵 須賀神社一帯) |
 |
上須恵山笠保存会が、毎年7月24日に一番近い日曜日に実施しているものです。 水法被姿の男衆は、重さ約1トンの飾り山を担ぎ、須賀神社をスタート。上須恵区・大島原区内の幹線道路を勇壮に駆け抜けます。詳しくは、上須恵須賀神社 「祇園山笠」をご覧ください。(別ページに移動します。) 【平成25年7月製作 12分59秒】 平成25年度文化芸術振興費補助金(文化遺産を活かした地域活性化事業) |
|
(大字植木) |
 |
甲植木区の地蔵盆です。町内で唯一、男の地蔵(道林寺)と女の地蔵(上組)に分かれお参りします。子どもたちが祭りの運営を行います。 【平成25年7月製作 10分48秒】 平成25年度文化芸術振興費補助金(文化遺産を活かした地域活性化事業) |
|
(大字植木 乙植木天満宮) |
 |
「四と四の十六文で祝うた~」と歌いながら家々を廻り、人々の無病息災を祈って、住民の頭に獅子舞をおしつけます。 【平成25年7月製作 12分38秒】 平成25年度文化芸術振興費補助金(文化遺産を活かした地域活性化事業) |
|
(大字須恵 須恵宝満宮) |
 |
宝満宮境内で作られた綱は、集落を清め、先祖の霊が西方浄土に帰る際の乗り物といわれています。集落内を廻り終えると綱を引きます。 【平成25年8月製作 11分30秒】 平成25年度文化芸術振興費補助金(文化遺産を活かした地域活性化事業) |
|
(大字佐谷 建正寺) |
 |
伝教大師最澄が開基したと伝わる建正寺。本尊の十一面観音立像は県指定有形文化財(彫刻)の第1号に指定されています。 寺に伝わる仏像は秘仏とされ、毎年4月の第1日曜日に御開扉の日に公開されます。境内にある佐谷神社の世話人会を中心にこの行事は行われ、地元を挙げての御接待が参拝者に振舞われます。 【平成26年4月製作 12分28秒】 平成26年度文化芸術振興費補助金(文化遺産を活かした地域活性化事業) |
|
(大字上須恵 須賀神社) |
 |
平成26年7月31日に行われた上須恵区須賀神社の夏越祭。茅を編んで茅の輪を作り、輪を潜って無病息災を祈ります。1週間ほど前に行われる須賀神社祇園山笠(町指定無形民俗文化財)が「動」の祭りとすれば、こちらの祭りは夏の夜に粛々と行われる「静」の祭りです。 【平成26年7月製作 13分58秒】 平成26年度文化芸術振興費補助金(文化遺産を活かした地域活性化事業) |
|
語り始めた黒ダイヤ ~新原から始まる炭鉱の歴史~<外部リンク> (大字旅石・新原) |
 |
須恵町新原に所在する炭鉱は、明治21年に海軍予備炭山に指定され、新原採炭所が置かれました。のち海軍採炭所、海軍燃料廠採炭部、戦後は国鉄志免鉱業所と名称を変更しながら、開坑から閉山まで国営であった唯一の炭鉱です。戦前は海軍、戦後は国鉄の炭鉱として我が国の発展を支えました。 新原公園は、海軍炭鉱第四坑の本部があった場所で、その地に今、海軍炭鉱に関係する資料が集まっています。 また、須恵第3小学校は、第六坑の跡地にあたり、小学校区の山の神区、恵西区、旭ヶ丘区、西原区には、閉山から約50年が経過するものの、炭坑住宅やその地割が現在も残っています。 【平成27年1月製作 14分48秒】 平成26年度文化芸術振興費補助金(文化遺産を活かした地域活性化事業) |
|
陶片は語る ~御用窯須恵焼に秘められた驚きの物語~<外部リンク> (大字上須恵) |
 |
今から約250年前の宝暦14年(1764年)、福岡藩士新藤安平がお殿様の恩返しのために始めた須恵焼の歴史をたどります。 個人創業で始まった須恵焼はのちに藩窯となり、幕末期には藩の殖産興業にとりあげられました。明治期には「金錆焼」と呼ばれる製品も焼かれ、中国・西洋に輸出されました。登り窯は上須恵区の皿山に現存し、現在県史跡の指定を受けています。 【平成28年11月製作 17分36秒】 平成28年度文化芸術振興費補助金(文化遺産を活かした地域活性化事業) |
|
(大字上須恵・須恵) |
 |
須恵町の田原眼科と岡眼科の歴史をたどります。江戸時代のはじめ、天草の浪人高場順正がこの地に眼科の技術を伝えて以来、現在に至るまで医業を生業とする田原家と岡家。その名は全国におよび、北は北海道、南は鹿児島から治療のために須恵の地を訪れました。須恵の目薬「正明膏」もまた、広く流通しました。近年の研究でその効能が実証されています。田原眼科、岡眼科に関わる人々の思いを伝えます。 【平成29年3月製作 23分33秒】 平成28年度文化芸術振興費補助金(文化遺産を活かした地域活性化事業) |
|
(大字旅石) |
 |
平成24年度に実施した須恵町大字旅石に位置する尋光寺の仏像修理の記録。修理により、200年前に一度修理を受けていたこと、その原因は江戸時代の文献に記載されていた台風であったこと、更には「法玄坊」という山伏が関係しており、その墓が今も旅石にあることが分りました。さらに、修理の中で、「幻の寺」とされていた海蔵寺がこの地にあったことが明らかになりました。 【平成24年7月製作 21分00秒】 |
| ほっけんぎょうの朝〈外部リンク〉 |  |
須恵町の正月行事である「ほっけんぎょう」。時代とともにその規模は縮小しつつありますが、現状の記録を行いました。【平成30年1月製作 16分49秒】 平成29年度文化芸術振興費補助金(文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業) |
| 数珠繰りの風景〈外部リンク〉 |  |
お堂で行われる数珠繰り。地域の人々が様々な願いを込めて行ってきました。【平成30年1月製作 16分23秒】 平成29年度文化芸術振興費補助金(文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業) |
| コロナ禍でも 変わらぬ願い 〜令和4年 須恵町の夏〜〈外部リンク〉
|
 |
コロナ禍の中、地域の伝統行事を再開させた須恵町の地域の人々の熱意を記録しました。 【令和4年8月製作 19分46秒】 |
民俗文化財欄内のリンク部分をクリックすると、Youtubeが新規ウインドウで開き、再生されます。
この記事に関するお問い合わせ先
社会教育課
〒811-2114
福岡県糟屋郡須恵町上須恵1180-1
電話:092-934-0030
ファックス:092-934-0035
メールでのお問い合わせはこちら






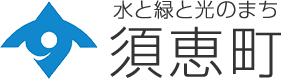



更新日:2023年03月10日